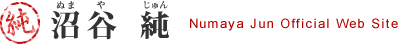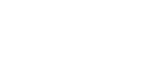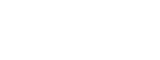仕事柄、県のHPは毎日見る。
議会で議論された予算や事業が、結果として、県民の皆様に向かってどのように発信されているのか、わかりやすさ、伝わりやすさも含めて、確認するのが仕事だと思っているし、県庁が日々発する膨大な情報を事前に全て把握することはできるわけもないということで、私自身、「こういう事業もやっているのか」と初めて知るというようなものも多い。
というような前置きはほどほどにして。
昨日、県のHPに、大変素晴らしい取り組みが掲載された。
「第29回国民文化祭 県民参加事業意向調査について」というものである。
詳細は、下記のURLからご確認をいただきたいと思うが、要は、
「国民文化祭において、県民の皆様自身が企画し、実施する事業を広く募集し、支援をしたい。」
「そこで、現時点で、どんな事業やアイディアがあるか教えてください。」ということを、呼びかけているものだ。
ここまでの手法は、特段、なにということはない。
しかし、ここから先が素晴らしい。
「支援は平成25年度に予定している。何件ぐらい採択できるか、一件あたりどのぐらいの助成額になるかは、応募状況を見てから検討する。」
となっている。
この、どこが素晴らしいかと言えば、これは言わば、「予算編成過程の公開」や「予算編成段階からの県民参加」ということに他ならないからだ。
これから県庁では来年度の予算を編成するための作業に入る。
このとき、当然、庁内では、各担当課が、様々なニーズや課題などを踏まえて、事業を作っていくし、関係する団体などから意見を聴きながら事業を作っていくというような流れになる。
国民文化祭を県民総参加で成功させようという趣旨からも、事業を作る段階、予算規模を決める段階から、広く意見を聴いて、立案していくというのは、日頃、なかなか県民の皆様からは見えない、縁遠い「県の予算編成」というものを県民の皆様に近づける大変良い取り組みだと感じた。
欲を言えば、助成金としての支援だけではなく、お金以外の支援についても広く意見を聴くような形も今後取っていっていただきたいと思うが、こうした県民参加型の予算立案というものが、県の様々な分野の中で行われていくことを期待したい。
日頃、敢えて県政に批判的な私が、ここまで手放しで激賞するのも珍しいな、と我ながら思いつつ(笑)
是非、多くのグループ、団体において、この予算編成の段階から、自らの希望などをお伝えいただきたいと思う。
詳細はこちらから(http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1350015853546/index.html)
先日、少し現地を見たいところなどがあり、雄勝郡をまわってきた。
雄勝郡は、岩手、宮城、山形と県境を接しており、昔から「南の玄関口」と言われてきたが、高速道路や新幹線などの高速交通体系の整備は未だ途上であり、実質的には、宮城方面、山形方面からの自動車・バスなどを利用した観光客がその主たるものになっている。
全県的に、温泉地は苦戦を強いられているが、雄勝郡もその1つ。
実は、小安、泥湯、秋の宮、栗駒と、全県的にみても、これほど趣やロケーションの違う、豊かな源泉を持つエリアはないと私は思っている。
男鹿や八幡平など、県内の観光復興の鍵を握る他のエリアも当然あるが、この雄勝郡こそ、名実ともに「南の玄関口」として、南東北からのマイカー客を秋田に引き込む、そのイントロダクションの役割を果たしていくべきだろう。
さて。
翻って、未来づくり交付金の話題。
先般、湯沢市からの「未来づくりプロジェクト」案が提出されたが、私にとっては大変残念なプロジェクトであったというのが率直な感想だ。
湯沢市が進めるジオパーク構想について異議はないが、プロジェクトに盛り込まれた事業を見ていくと、湯沢市内の公園整備・改修など、既存施設のリニュアルが大半を占めていた。
これは湯沢市に限らず、この交付金制度全体の大きな欠陥だと私は思っているのだが、25の市町村が、それぞれ近隣市町村との連携や協働もなく、単体で事業を組むことで、波及効果やスケールメリットが小さくなるばかりか、他市町村との住み分けも難しいような事業が多々出てくることになる。
さきほど、挙げた温泉群は、東成瀬村と湯沢市にまたがるわけだが、こうした市町村の単位を超えた連携プロジェクトにむしろ県が交付金を支出するというのが、県と市町村の本来の関係なようにも思われ、今後、どの市町村からどのようなプロジェクトが出てくるかは定かではないが、市町村が保有する施設や設備の更新や補修を、自主財源では賄えないから、県の交付金を活用してやってしまおう、などというものがあったらなら、それは「未来づくり」に名を借りた単なる財源振替となる。
本来、市町村の責任において行うべき、施設設備の維持管理・更新を、県がその費用の一部を肩代わりするとなれば、それは市町村の財政規律、責任というものを曖昧にし、ひいては、県の役割や財政規律にも大きな影響をもたらしかねない。
こういうことはやるべきではないと思う。
少し話が飛ぶが、国会議員の方々はよく、「地元のためになにしてけだのよ」と言われるようだ。
国会議員は日本のために働くのだが、やはりどこかで有権者の方々のそうした「期待感」があることもよく
理解できる。
日本を良くすること、日本の社会制度をより良いものにしていくことが、秋田のため、地元のためになるのだ、という理屈は正論であるが、ストレートには伝わりづらい。
このことを我々県議会議員に当てはめればどうなるか。
秋田県全体のために働くのが我々の仕事、ではあるが、それぞれの選挙区では、様々な地域課題や要望があり、そこに向き合うということも求められる。
さらには、ときに市町村議会議員のような、まさに居住地の地域課題にも微力ながらお手伝いをさせていただくこともある。
しかし、やはり、そういうことがありながらも、県議会議員の本懐たる「秋田県全体のために」という大局に立った仕事をしていかなくてはならないし、その結果、地元の方々に対峙してでも厳しいことを言わなくてはならぬこともまたあるだろう。
グローカルな議員にはなりたいが、単にローカルな議員にならぬよう気をつけたい。
我が民主党が秋田3区で擁立しようとしている方のお名前が地元新聞紙によってオープンとなった。
三井マリ子さんという女性で、横手市出身であるが東京都議を務めるなど、幅広くご活躍されてきた方であり、正式に公認あるいは出馬ということになれば、秋田3区の支部長として秋田での活動をスタートさせることになるだろう。
これからの日本の大きな政策課題である社会保障問題、負担と給付のあり方、社会構造というものを考えていくとき、日本人の半分が女性なのである以上、女性の視点でそうした社会保障政策がもっともっと議論されていかなくてはならないことは自明であり、民主党という一政党の枠を超えて、女性の視点の必要性はより一層高まっていくだろう。
社会保障は、少子高齢化が進む秋田県にとっても根本的なテーマであり、その意味でも、この社会保障政策に知見を持っておられる三井さんが果たせる仕事、役割は大きいだろうと思う。
私自身、短い時間ではあったが、直接お話をする機会があったが、快活で、持論もしっかり持っておられる方だと感じた。
これが決まれば、民主党としては1区、2区、3区ともに候補者が出そろい、対する自民党も決まっており、その他の政党についても、まだ若干の動きはあれども、大方のところは想定の範囲内の方々が想定どおりの動きをされるのではないかと思われるので、これでつまり、この後の衆院選の戦いの輪郭というのが定まってきた、ということになるだろう。
あとは、それぞれの政党がどういう選挙公約を掲げるか、ということだが、「マニフェスト違反」といった、これまでの国民の皆さまから批判や誹りがいかにあろうとも、やはり、次の選挙もまた民主党として公約を掲げて戦うことが当然だとも思っている。
そういう中で、おまえは何をやるんだ、ということになるわけだが、来るべき総選挙での私自身の役割は、もちろん必要があれば全県どこなりとも各候補者のサポートに走るということは当然だが、各候補者とも、私よりずっと政治経験が長く、私ごときがそのへんをウロチョロするのはむしろ僭越、というようなこともある。
むしろ、裏方として、民主党が掲げる政策、あるいは抱える国政課題といったものと、秋田県にとって必要・有益な政策、解決すべき課題といったものを結び付る、その「繋ぎ目」のような役割を担えれば、と考えている。
なにより、民主党秋田という1つの組織体が、円滑に、矛盾なく、一体で動いていけるよう、私自身微力ながらやっていきたいと思う。